「ワインってどんなお酒なんだろう?よく飲むけど知らないことが多い」
「ワインに苦手意識がある。もっと美味しく飲む方法はないのだろうか」
ワインは私たちにとって身近なお酒で、コンビニやスーパーでもたくさん売られています。
しかし深く調べると、普通では気づかないさまざまな種類・作り方・飲み方があるのです。
これらを知ることで、これまで以上にワインを美味しく飲めるでしょう。反対に、知らないままワインを飲むと、本当の味を知らず損をしてしまうことも。
そこでこの記事では、ワイン初心者でもわかりやすいようにワインに関する基本的な知識をまとめました。
本記事を、ワインを楽しむための第一歩としてください。
ワインとはどんなお酒なのか

世の中に流通しているお酒は、次の3つに分類されます。
- 醸造酒:穀物や果物を酵母でアルコール発酵させたお酒
- 蒸留酒:醸造酒を蒸留(溶液を沸騰させ発生した蒸気を冷やして液体として回収する)したお酒
- 混成酒:醸造酒や蒸留酒に糖分・果汁などを加えたお酒
このうち、ワインは醸造酒に当たります。ビールや日本酒も醸造酒の一種です。
醸造酒の中でも原料によってさらに種類が分かれ、ワインは果実を使って作られるお酒です。ビール、日本酒は穀物を使って作られます。
ワインは果実に含まれる水分を使って作られるため、仕込みの水は不要です。ブドウ(果実)の品種や質のよさによってワインの美味しさは決まります。
ワインの原料はブドウだけではありません。リンゴやモモなどが原料となる場合もあります。
このようなワインは「フルーツワイン」と呼ばれ一般的なワインとは別に扱われることもありますが、製造方法はワインとほとんど同じです。

ワインは古い歴史をもつお酒
ワインは約8000年前にあたる紀元前6000年ごろから飲まれていたという説もあり、長く人類に愛されてきたお酒だとされています。
またエジプトの壁画にブドウを栽培する様子が描かれていたり、旧約聖書にワインに関する言及があることも歴史を物語っているのです。
ここまで古い歴史をもつ背景には、ワインの製造方法が関係しています。
ワインはブドウを潰し、皮に含まれる酵母で発酵させるため、工程としてはかなりシンプル。そのためお酒の技術に乏しかった時代でも製造することができたとされています。
ワインの主な生産国
ワインは世界各地で生産されています。
有名な国で言えば「フランス」「イタリア」「ドイツ」あたりはご存知の方も多いでしょう。
ヨーロッパではその他に「スペイン」「ポルトガル」でも生産が盛んです。
また「アメリカ」は世界4位のワイン生産国であり、その南に位置する「チリ」「アルゼンチン」も世界有数のワイン生産国と知られています。
他に南半球では「オーストラリア」「ニュージーランド」「南アフリカ」が有名です。
アジアでは「中国」が1990年代から生産量を伸ばしています。「日本」も2000年代に入ると品質が高まり、ワイン生産国として注目されるようになりました。

日本のワインの消費量
ワインに関する豆知識として、日本のワイン消費量を見てみましょう。
国税庁発表の資料によると、日本のワインの総消費量は調査を開始した1976年から高まり続けており、1989年には11万2,777キロリットル、2018年には35万2,046キロリットルにまで上昇。平成の間で消費量はおよそ3倍も増えています。
この背景には1989年に改正酒税法が施行され、酒類の販売規制が緩和されたことや、ワインの値下がりが影響しているとみられます。
ワインの種類
続いて、ワインにはどんな種類があるのかを紹介。
大きく、次の4種類に分類されます。
- スティルワイン
- スパークリングワイン
- フレーバードワイン
- フォーティファイドワイン
スティルワイン
赤ワイン、白ワイン、ロゼワインといった一般的なワインのことです。
炭酸ガスを含んでおらず、次に紹介するスパークリングワインがシュワシュワと泡を立てて動いているのに対し、動きがなくじっとしていることから「スティルワイン」と呼ばれています。

スパークリングワイン
炭酸ガスを含んだワインのことです。
聞き慣れた人も多いであろう「シャンパン(シャンパーニュ)」はスパークリングワインに分類されます。
フレーバードワイン
ワインに果汁やスパイス、薬草などを加えて風味づけしたものです。
サングリアやベルモットなどのワインがフレーバードワインに分類されます。
フォーティファイドワイン
ワインにブランデーなどの強いアルコールを加えて、アルコール度数を高めたものです。
「酒精強化ワイン」とも呼ばれ一般的なワインよりもアルコール度数が強く、15%以上になります。

ワインの作り方

古くから多くの人々を魅了し、今でも世界中で愛され続けているワイン。
そんなワインはどのようにして作られているのでしょうか。
「赤・白ワイン」「ロゼワイン」「スパークリングワイン」「甘口ワイン」それぞれの作り方を解説します。
赤ワイン・白ワインの作り方
赤ワインは黒ブドウの果汁と果皮を発酵させて作ります。
作業工程は以下の流れです。
- ブドウの収穫
- 発酵
- 圧搾
- 熟成
- 瓶詰め
- 瓶内熟成(ワイン瓶内のわずかな酸素で酸化させ、味わいをまろやかにする)
白ワインは白ブドウの果汁を搾り、発酵させて作ります。
作業工程は以下の流れです。
- ブドウの収穫
- 圧搾
- 発酵
- 熟成
- 瓶詰め
- 瓶内熟成
赤ワインと白ワインの作り方は基本的に同じステップを踏みますが、収穫したブドウを搾るタイミングが異なります。
白ワインはブドウを搾って果汁のみを発酵させますが、赤ワインはブドウを潰して皮とタネも一緒に発酵。
これにより赤ワインには皮に含まれる色素と、種に含まれる渋さ(タンニン)が現れるのです。
白ワインは赤ワインのようなブドウの色をしておらず、渋さがありません。それは作り方の違いによって生み出されています。
ロゼワインの作り方
ロゼワインにはいくつかの製造方法がありますが、主流とされているのは赤ワインと同じくブドウの皮と種も一緒に発酵させる方法です。
赤ワインとロゼワインに明確な差はありません。違いとしては、ある程度色を汲み出したら皮と種を取り除くという点があります。
これにより赤ワインのように色が濃くならず、薄いロゼワインのバラ色が保たれるのです。
製造の工程は以下の流れ。
- 収穫
- 発酵
- 圧搾
- 発酵
- 熟成
- 瓶詰め
- 瓶内熟成
スパークリングワインの作り方
スパークリングワインは製造工程の中で2回の発酵を行います。
1回目(一次発酵)はスティルワインと同じく、アルコールを得るための発酵です。ここまではスティルワインと同じ作り方になります。
次に行う発酵(二次発酵)は、泡を得る目的で行います。二次発酵は2つの種類に分けられ、ワインの瓶内で泡を作る「伝統的製法」や「瓶内二次発酵製法」と呼ばれる方法と、巨大なステンレスタンクの中で圧力をかけて発酵させる「シャルマ法」という方法があるのです。
伝統的製法は手間がかかるものの複雑な味わいを生むことが可能であり、シャルマ法は量産が可能で果実の新鮮さが保たれるという特長があります。
二次発酵の後、リキュールをどれくらい入れるかによってスパークリングワインの味が変わります。
リキュールを入れていない段階では辛口、リキュールを多く入れるほど甘口になるのです。
甘口ワインの作り方
甘口にワインには糖度の高いブドウが必要となります。
ブドウの糖分は酵母によってアルコールに変えられ、糖分が多いほどアルコールが増え、辛口のワインになるのが一般的です。
しかし極端に糖分が多いブドウを使うと、酵母がアルコールに変えきれなかった糖分が残り、甘口のワインが出来上がります。
主に次の方法で糖度の高いブドウから甘口ワインを作り出します。
「遅摘み」
通常より収穫時期を遅らせることで糖分が凝縮したブドウを使ったワイン
「陰干し」
ブドウを干してレーズンのようにして糖分が凝縮したブドウを使ったワイン
「貴腐」
特殊な菌(ボトリティス・シネレア)が付着し、生きたまま乾燥したブドウを使ったワイン
「アイスワイン」
氷点下で水分が凍りついたブドウを圧搾して作るワイン

ワインに合う料理を種類別に紹介
ワインは「食中酒」とされており、基本は料理と一緒に楽しむお酒です。
ワインによって合う料理も異なっており、どんな料理がピッタリなのか知っておくと一段と美味しくワインを飲めることでしょう。
どんな料理が合うかを考えるときに重要なのがワインの「色」「味」「産地」。
ワインと料理の色を合わせると双方とも美味しく楽しめるとされています。
またあっさりした味わい(ライトボディ)のワインには料理も軽めのものを、アルコール度数の高い赤ワインや味が濃厚なワイン(フルボディ)には同じく味の濃い料理が合うとされているのです。
さらに産地も合わせるとなおよし。イタリアワインならイタリア料理を、フランス料理ならフランス料理を合わせると美味しく感じられるでしょう。
ここではオーソドックスな「赤ワイン」「白ワイン」「ロゼワイン」「スパークリングワイン」に合う料理の例を紹介します。
お食事の際にぜひ参考にしてください。

赤ワインには色が赤い・濃い料理が合う

赤ワインには色が赤い、あるいは濃い色をした料理が合います。
代表的なもので言えば肉料理です。ジューシーなお肉と濃厚な赤ワインがマッチし、食欲を一層満たしてくれるでしょう。
【おすすめの料理】
- ステーキ
- ハンバーグ
- ハム
- ビーフシチュー
など
白ワインには色が薄くあっさりとした料理が合う

赤ワインとは反対で、あっさりとした味わいのものが多い白ワインには、色が薄くあっさりとした料理がおすすめです。
特に魚介系の料理と一緒に楽しむと、ワインも料理もさらに美味しく感じられるでしょう。
【おすすめの料理】
- 魚介類を使った料理
- 豚しゃぶ
- 焼き鳥
など
ロゼワインは和・洋・中さまざまな料理と合う

ロゼワインはどんな料理とも合うオールラウンダー。和食・洋食・中華、さまざまな料理と合わせてお楽しみいただけます。
おすすめな選び方ととしては、ロゼワインの色と料理の色を合わせるという方法。濃いロゼワインには色の濃い料理を、色の薄いロゼワインにはあっさりとした味付けの色の薄い料理を選んでみてください。
【おすすめの料理】
- 魚の煮付け
- 肉じゃが
- 唐揚げ
- エビチリ
- シュウマイ
- ポテトサラダ
- パスタ
など
スパークリングワインにはどの料理も合い食前酒にも最適

ロゼワインと同じく、スパークリングワインもどの料理にもピッタリです。
また食前酒としても最適。複数人で食事をする際、乾杯はスパークリングワインで行うのもいいでしょう。
【おすすめの料理】
- サラダ
- アヒージョ
- 餃子
- 鍋料理
など
ワインを美味しく飲むために意識したいポイント

ワイン飲み方、それは「グラスに注いで喉に流し込む」。
確かにこれに尽きるのですが、もう少し工夫をすることで何倍もの美味しさを引き出すことが可能です。
ここからはワインを美味しく飲むために意識したいポイントを解説します
特に次のような方は意識すると、ワインに対するイメージが大きく変わることでしょう。
「これまであまり何も拘らずワインを飲んできた」
「ワインを飲んだことはほとんどない」
「ワインは渋くてあまり好きではない」
飲みやすいワインを選ぶ
そもそもどんなワインを飲むのか、ワイン選びからこだわりましょう。
ワイン初心者は、まずスパークリングワインや白ワインからチャレンジするのがおすすめ。理由は比較的クセがなく、飲みやすいと感じる人が多いためです。
購入の前にアルコール度数もチェックしてください。一般的にワインのアルコール度数は12%前後。これより低い度数のものもあるので、最初は低いものを選ぶと「飲みやすい」と感じられ、ワインを好きになれるでしょう。
食事と一緒に楽しむ
先ほども紹介したようにワインは「食中酒」で、食事と一緒に楽しむのが基本です。
ワインを飲む際はぜひピッタリな料理を一緒に召し上がることをおすすめします。
本記事で紹介したようなワインに合う料理を用意するのもいいですが、最初はあなたの好きな料理と一緒に飲んでも構いません。
特にロゼワインやスパークリングワインはさまざまな料理とマッチする万能なワイン。好きな料理と組み合わせても美味しく飲めるでしょう。
カクテルにする

「買ったワインのアルコールが少し強く感じた」「少し味に苦手意識を感じた」という場合は、カクテルにして飲むのはいかがでしょうか。
ジュースや炭酸で割ることにより、ワインの独特なクセや渋みを抑えられます。ワインが苦手という方でも飲みやすくなるでしょう。
実際にワインを使ったカクテルもあり「キール」や「フーゴ」が有名です。

サングリアにする

また違ったワインの楽しみ方として、サングリアにするというのもおすすめ。
サングリアとは、ワインにフルーツを加えて飲むこと。スペイン南部発祥の飲み方とされています。
ワインに好みのフルーツを切って漬け込むことで完成するという手軽さも魅力です。
サングリアにジュースや炭酸を加えれば、よりアルコール度数を下げられ飲みやすくなるでしょう。

ワインを空気に触れさせる
映画やドラマなどで、お金持ちの人がレストランでワイングラスをクルクル回しているシーンを見たことはないでしょうか。
あれは、ただおしゃれな雰囲気を作っているわけではなく、きちんと意味のある行動なのです。
グラスに入ったワインをクルクル回すことを「スワリング」と呼びます。ワインを空気に触れさせることで香りを引き出し、味をまろやかにすることを目的に行う作法です。
回す回数は2〜3回で十分とされています。
ワインは空気に触れさせることで風味が変化します。スワリングによってワインが美味しく飲める場合もあるので、ぜひ試してみてください。
別の方法として、ワインをガラスの瓶(デキャンタ)に移して空気に触れさせる「デキャンタージュ」もあります。
ワインの温度を調節する
ワインには種類によって美味しく飲める温度も異なります。
ワインの種類と合わせて適切な温度もぜひ知ってきましょう。
- 赤ワイン:12〜20度(常温で20度以下がおすすめ)
- 白ワイン:6〜12度
- ロゼワイン:8〜12度(薄い色は8〜10度、濃い色は10〜12度がおすすめ)
- スパークリングワイン:6〜8度
ワインを冷やす際はワインクーラーを使うのがおすすめです。ワインクーラーに氷水を入れて冷やしましょう。

知識があるとワインを何倍も美味しく楽しめる
本記事で紹介した内容は、ワインに関する知識のごく初歩的な部分のみです。
ワインの世界はもっと深いのですが、基本の知識があるだけでもワインの楽しみ方は変わってきます。
この記事を読んだあなたは、これまでの何倍もワインを楽しめるようになっているはず。
これをきっかけに、ぜひワインに関する知識を深めてみてください。







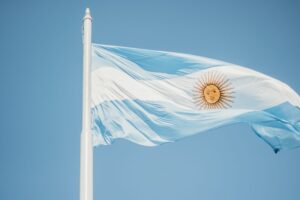


コメント