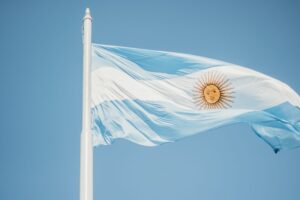ワインには「ボディ」と呼ばれる言葉があり、「フルボディ」「ミディアムボディ」「ライトボディ」の3つに分類されます。
ワイン初心者にとってはあまり聞き慣れない言葉でしょう。
そこでこの記事では、ワインの「フルボディ」を中心に解説。「ミディアムボディ」「ライトボディ」との違いも紹介します。
ワインの「ボディ」とは

「フルボディ」の意味を理解するためには、まず「ボディ」とは何かを知っておくと分かりやすいでしょう。
「ボディ」とはワインの重みや渋み、コク、力強さ、飲みやすさなどを表現する専門的な用語です。
ワインの味わいは、もともと「男性的」「女性的」という言葉を使って表現していました。そこから派生して「ボディ(身体)」という表現が一般化した背景があります。
また「ボディ」は主に赤ワインの味わいを表すときに用いられます。
「フルボディ」の意味
フルボディは、ワインの中でも重みがあり、渋み、コクが強く飲みごたえのある力強いワインという意味で使われる言葉です。
見た目の色が濃く、香りも深いワインに対して「フルボディ」という表現を使います。
「フルボディ」のワインにはアルコール度数が12%を超える強めのものが多いですが、アルコール度数だけでボディは決まりません。
フルボディでもアルコール度数が低いワインもあります。

「ライトボディ」と「ミディアムボディ」
ワインのボディは「フルボディ」だけでなく「ライトボディ」と「ミディアムボディ」を合わせて3つに分けられます。
「ライトボディ」と「ミディアムボディ」の特徴も見てみましょう。
ライトボディ
「ライトボディ」とは簡単に説明すると「さらりと飲めるワイン」のことです。
渋みが少なく軽い口当たりで飲みやすいと感じる方も多いでしょう。
またアルコール度数が低いワインが多いのも特徴です。
初めてワインを飲む方や、ワインに対して苦手意識がある方はライトボディのワインから飲み始めるのがおすすめ。
ミディアムボディ
「ミディアムボディ」は「フルボディ」と「ライトボディ」の中間的な味わいのワインです。
ライトボディ→ミディアムボディ→フルボディの順で重厚感が増していきます。
「ミディアムボディ」のワインは味のバランスがよく、魚介系の料理に合うのが特徴です。
「ライトボディ」のワインを飲み慣れたら「ミディアムボディ」に挑戦してみるとよいでしょう。
ボディの違いに明確な基準はない
ここまで3種類のボディについて説明してきましたが、実はボディの違いに明確な基準はありません。
ワインを作ったメーカーが独自の判断で決めている場合が多く、飲む人によっても評価は変わるのです。
同じライトボディのワインでも「コクが強い」「少し飲みにくい」と感じる人もいれば、フルボディのワインでも「渋みがない」「飲みやすい」と感じる人もいます。ボディは目安と考えましょう。
初めてのワインを買う場合は、可能であれば試飲して味や香りを確かめることをおすすめします。
赤ワイン以外を「ボディ」と表現しても間違いではない

先ほども触れましたが、ボディという表現は赤ワインに対して用いるのが一般的です。
白ワインは「辛口」「甘口」と表現します。ロゼワインやスパークリングワインも同様です。
しかしこの限りではなく、重い味わいの白ワインをフルボディ、軽い味わいの白ワインをライトボディと呼んでも間違いではありません。
ボディは何によって決まるのか

続いて、ワインのボディは何によって決まるのかを解説します。
明確な基準はないものの、主に次の3つの要素で決まるのが一般的です。
- アルコール度数
- ブドウの品種(タンニン)
- 熟成に使用する樽
アルコール度数
ワインのアルコール度数は味わいに大きく関係し、度数が高くなるほど強いコクを感じやすくなります。
つまりアルコール度数が高いものはフルボディのワインに分類されることが多いのです。
ただ先述の通り、ワインのボディはアルコール度数によって決まるわけではなく、「何度以上のワインはフルボディ」といった基準はありません。
「フルボディはアルコール度数が高いワインが多い」「ライトボディはアルコール度数が低いワインが多い」くらいの認識でいましょう。
ブドウの品種(タンニン)
ワインの原料として利用されるブドウ。このブドウの品種によってもボディが決まります。
正確には、ブドウに含まれる「タンニン」と呼ばれる成分が多いほどワインに渋みが生まれ、フルボディのワインに使われやすいのです。
日照時間が長い地域や、温暖な気候の中で育ったブドウはタンニンが豊富に含まれるものが多いという特徴があります。
熟成に使用する樽
ワインは製造の過程で「熟成」というステップを踏みます。この際に使用する樽もボディに大きく関わるのです。
木製の樽を使って熟成させると、ワインのコクや香り深く、強くなるとされています。
また樽に使われている木の匂いがワインと混ざり、複雑な香りを生むことも。
つまりフルボディのワインになりやすくなるということです。
一方、ライトボディが多い新酒などは熟成の際に木製の樽を使用しません。
使用するブドウの品種をボディごとに紹介

ワインのボディはブドウの品種によっても決まるということを説明しました。
では、実際にどのような品種が使用されているのでしょうか。代表的なものをボディごとにまとめました。

フルボディに使われる主なブドウの品種
「カベルネ・ソーヴィニヨン」
長い期間熟成させるワインに向いており、ワインに強い香りや渋み、コクを生み出す品種です。
「マルベック」
タンニンの量が多く、しっかりとしたフルボディのワインを生みます。
「シラー」
香りがスパイシーで、ワインに渋みを生むタンニンや酸味を多く含んでいます。
ミディアムボディに使われる主なブドウの品種
「サンジョヴェーゼ」
イタリアで収穫されることの多いブドウで、栽培方法によって酸味のあるワインにも、重厚感のあるフルボディにもなります。
「ピノ・ノワール」
甘い香りが特徴的で、タンニンの量が少なく渋みもやや控えめです。
「メルロー」
酸味が抑えられ、マイルドな飲み口のワインになります。
「テンプラニーリョ」
他のブドウに比べ早熟な品種です。適度な酸味と控えめながらしっかりとした渋みのあるワインを生みます。
ライトボディに使われる主なブドウの品種
「カベルネフラン」
タンニンが少なく、木苺のような香りのするワインを生み出すブドウ品種です。
「ガメイ」
有名なボジョレー・ヌーボーにも使用されているブドウ。フルーティなワインにも、強く香りを持つ重厚なワインにもなります。
「ピノ・ノワール」
非常に繊細で栽培が難しいとされるブドウ。口当たり、香りのよいワインを生み出すことで愛好家からも人気の高い品種です。
フルボディのワインを美味しく飲むポイント

フルボディのワインはアルコール度数が高めで、重厚な口当たりのものが多く「飲みにくい」と感じる人もいることでしょう。
特にワインを飲み慣れていない方は、少し苦手意識を感じてしまうかもしれません。
そこで、フルボディのワインを美味しく飲むためのポイントを紹介します。
温度は常温に近く
ワインは種類によって美味しく飲める温度があります。
フルボディのワインは常温くらい、16〜18℃くらいにして飲むといいでしょう。
あまりに冷やしすぎるのも、高い気温の中で保存するのもおすすめできません。
ちなみに、ライトボディは10~12℃くらいの低めの温度で、ミディアムボディは13〜16℃くらいがおすすめです。
空気に触れさせる
ワインは空気に触れさせることで味わいや香りが変わります。
ワインを飲むとき、グラスをクルクルと回している人を見たことがないでしょうか。あの仕草は「スワリング」と呼ばれ、ワインを空気に触れさせているのです。
フルボディのワインを飲むときも、グラスを2〜3回ほど回してスワリングするとまた違った味わいを楽しむことができるでしょう。
あるいは、ワインを瓶からデキャンタに移す「デキャンタージュ」という方法で空気に触れさせるのもおすすめです。
ワインを飲む状況に合わせてボディも考えよう
ワインは「食中酒」と呼ばれており、食事と一緒に飲むのも楽しみ方の一つです。
ワインの種類やボディによってマッチする料理も異なるため、買う際はどんな状況、食事の場で飲むワインなのかを考えると、ぴったりなものを選べるでしょう。
例えば、フルボディの赤ワインにはステーキやハンバーグといった肉料理がおすすめです。
本記事をお読みいただいたあなたは、フルボディのワインに関する知識を十分に身につけました。これからは自信を持ってフルボディのワインを選び、お楽しみください。