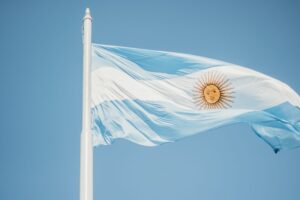ワインの世界は奥が深く、種類、飲み方、熟成期間など一概には説明できないほど多様です。
実はワインだけでなく、ボトルの飲み口を塞ぐために使われる「コルク」にも様々な種類や歴史があります。
本記事ではワインとセットでイメージされることの多いコルクについて解説。ワイン博士の第一歩を踏み出せるような豆知識が多めの内容となっています。
コルクとは何か

コルクとは主に木製の栓のことを意味し、ワインボトルの口を閉じるために使われるものです。
コルクの材料は「コルク樫」と呼ばれる木であり、この木は地中海周辺で育っています。
ヨーロッパにワインの産地が多いことを考えると、コルクが地中海付近で育つ木を使って作られるのも納得がいきます。
特にポルトガルで多く生産されており、世界で流通するコルクの約7割がポルトガル産です。
コルクは樹皮(木の皮)を使って作られるため、木を伐採する必要はありません。樹皮は再生し、それを使ってまたコルクを生産できるため、環境にも優しい栓であることがわかります。
コルクの種類
コルクと聞いてイメージするのは木製のものでしょう。
実はコルクには複数の種類があり、使われている素材も違うのです。
ここではコルクの種類とそれぞれの特徴を解説します。
天然コルク
冒頭で説明した樹皮を使ったコルクが、この「天然コルク」です。
樫の木から剥がした樹皮を円筒形にくり抜いて作り出します。
伸縮性・弾力性に富んだ触り心地が特徴。また腐食に強い、水や油を通しにくい、燃えにくいなど普通の木とは異なる性質がワインの保存に向いています。
圧搾コルク(テクニカルコルク)
天然コルクをくり抜いた後の樹脂を砕き、接着剤で固めたものが圧搾コルク(テクニカルコルク)です。
天然コルクの残りの材料で作れるため、無駄がないのが特徴。また天然コルクより安価で作れるというメリットもあります。
一部天然・一部圧搾コルク
天然コルクと圧搾コルクを混ぜ合わせたコルクです。
コルクの上と下のみが天然、中は圧搾コルクでできています。
安価でありながら、天然コルクのように見えるという点が特徴です。
スパークリングワイン専用コルク
スパークリングワインのボトルの栓として使われる特殊なコルクです。
普通のコルクに比べ、上の部分が大きく膨れ上がったような作りになっており、キノコのようにも見えます。
スパークリングワインにとって重要な炭酸が抜けにくい、密度の高いコルクです。
このコルクを開ける際は、スクリュー型のワインオープナーやソムリエナイフは使わないようにしましょう。密度の高いコルクのためワインボトルに負担がかかり、割れてしまうリスクがあります。
樹脂製コルク(プラスチックコルク/合成コルク)
樹脂製コルクはシリコンなどの樹脂を使って作られ、プラスチックコルクや合成コルクと呼ばれることもあります。
かつての樹脂製コルクはワインにたくさんの酸素が入ってしまうことから、安価なものにだけ使われていました。
昨今は酸素の侵入を防ぐ密閉度の高い樹脂製コルクが開発されており、長期熟成が必要なワインに使えるものも増えています。
しかしかつてのイメージから、今でも樹脂製コルクは安いワインの栓として使われるのが一般的です。
コルクの歴史には諸説あり
コルクがいつからワインの栓として使われるようになったのかには諸説あり、はっきりとしていません。
1600年代にガラス瓶が生まれ、それ以降コルクが使われるようになったことから1700年代から使われていたという説もあれば、コルク自体は2000〜4000年前にあったという説も。
ガラス瓶とコルクはワインの長期熟成・長距離の運搬が可能になるなど、革命的な開発だったことは間違いありません。
コルクにキャップシールがついている理由

お店で販売されているワインを見ると、コルクの上にキャップシールがついています。
このキャップシールはコルクの乾燥を防ぐためのものです。
コルクが乾燥すると縮小して密度が下がり、酸素の透過量が多くなってしまいます。これによりワインの酸化を進めてしまう可能性もあるのです。
そのような事態を防ぐためにキャップシールがついています。
コルクの長さの違い
コルクはワインの種類によって長さが異なります。おおむね3〜6 cm ほどの開きがあるのです。
長期熟成させるワインほど長いコルクが使用され、5.5 cm以上のものが使われるのが一般的。
長いコルクほど密閉度が高くワインが酸化しにくく、味の劣化スピードが遅くなるという特徴があります。そのため長期熟成に向いているのです。
コルクに入っている刻印
コルクをワインボトルから引き抜くと、表面に刻印が入っていることがあります。
これは、ワインが本物か偽物かを区別するためにつけられたものです。
20世紀初頭、ワインの偽物が多く流通するようになりました。そこで本物かどうかを見分けるため、コルクにシャトー名(フランスのボルドー地方にブドウ畑を所有し、ワインを製造している生産者に与えられた名前)やヴィンテージ(原料のブドウを収穫した年)などが刻印されたという背景があるのです。
コルクは「ブショネ」に注意
ワインの保存に向いており、環境にも優しいコルク。いいとこずくめのように思えますが、注意点もあるのです。
コルクによって「ブショネ」という現象が起きることがあります。ブショネとは、コルクの汚染によってワインの品質が劣化してしまうことです。
ブショネはコルクに含まれた細菌や消毒に使われる塩素によって生まれる TCA (トリクロロアニソール)という物質によって引き起こされます。
高いワインであればブショネが発生しないというわけではなく、どんなワインでもブショネは起きうるのです。その可能性は約5%とされています。
もしレストランなどで飲んだワインが不快な香り・味がした時はブショネの可能性があるため、お店の人に伝えて交換してもらいましょう。
ブショネの対策は進んでいる
昨今はブショネを防ぐための対策も進んでいます。
先ほど紹介したコルクの1つである樹脂製コルクや、スクリューキャップはブショネが発生するリスクがありません。
ブショネが心配な場合は、樹脂製コルクやスクリューキャップのワインを購入するといいでしょう。
コルク以外に使われている栓
スクリューキャップの話題が出たため、ここでコルク以外に使われている栓の種類も紹介します。
主に次のような栓を見かけることが多いでしょう。
- スクリューキャップ
- ゾーク栓
- ガラス栓
- 王冠
スクリューキャップ
その名の通り、回転させながら開けるキャップです。
最近はコルクではなくスクリューキャップを使っているワインも増えています。
特にアメリカ、チリ、オーストラリア、ニュージーランド産のワインはスクリューキャップで栓をしているものが多く見受けられます。
ブショネが発生しない、ワインオープナーが不要などのメリットがありますが、安価なワインに使われているというイメージがいまだに根付いている様子。スクリューキャップは高級なワインにも使われているため、栓だけでの判断は禁物です。
ゾーク栓
プラスチック製で、スパークリングワインに用いられることの多い栓です。
ブショネやワインの酸化を防ぐ新しい栓としてオーストラリアで開発されました。
ガラス栓
コルクに似ていますが、素材は木製ではなくガラスを使用しています。
素手で開閉ができるというメリットがある栓です。
王冠

スパークリングワインの栓として使われます。ビール瓶にも見られる栓です。
スティルワインで王冠が使われていることはまずありません。
ワインオープナーがないときの対処法

コルク栓を開ける時は、ワインオープナーを使うのが基本です。
しかしワインをあまり飲まない人だと、手元にオープナーがないということも。
そこで余談のような内容にはなりますが、ワインオープナーがない時のコルクの開け方を紹介します。
ネジとドライバーを使う
コルクにネジを挿し、ドライバーで回します。ネジがある程度コルクに埋まったら、てこの原理を使って引き抜きましょう。
ペンチでネジを掴むと引き抜きやすいです。
仕組みはほぼワインオープナーと同じ。簡易的なオープナーを作るやり方だとお考えください。
ボトルの底を壁や床に打ちつける
この方法はワインボトルが破損する恐れがあるので、注意して行ってください。
ワインボトルの底を厚手のタオルで包み、壁や床に底面を打ちつけます。すると段々とワインボトルが上がってきて、取れやすくなるという方法です。
勢いよくコルクが飛び出すこともあるため、周りに人がいない場所で行うようにしましょう。
コルクはワインのイメージにも影響を与えている
コルクとガラス瓶の登場によってワインは大きく進化。楽しみ方のバリエーションが広がりました。
ワインはコルク栓の方がおいしいと感じる人もいるなど、イメージにも大きく影響を与えているようです。
コルク栓のワインとそれ以外のワインを飲み比べてみて、どちらが美味しく感じるか調べてみるのも面白いでしょう。